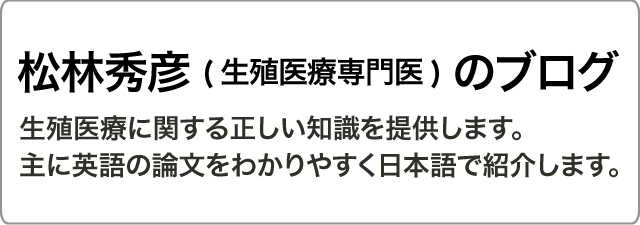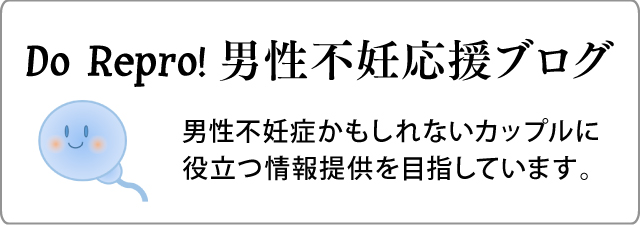習慣性流産は、200組に1組の割合とされており、習慣性流産の原因として、染色体異常の一種である「均衡型転座」は、4.5%とのこと。
倫理委員長によりますと、子供を授かる確率は、着床前診断を実施しても、しなくても、変わらないことから、今回の決定は、流産を繰り返すことによる精神的肉体的苦痛の緩和のためで、決して、着床前診断によって、必ず、子供が授かるようになれる夢の治療でないことを強調しています。
また、実施には、遺伝カウンセリングの実施や実施施設の資格要件、個別審査等の条件を課すとしています。
コメント
着床前診断とは、体外受精で得た胚を、受精後2~3日目の4~8個の細胞分裂した時点で、胚から1部の細胞を取り出して、染色体や遺伝子の異常の有無を検査し、問題のなかった胚のみを子宮に移植する診断技術のことです。
染色体異常が原因の習慣性流産をを対象とした着床前診断の実施申請が、昨年来、相次いだことから、学会の見解が注目されていました。
そして、今回、これまでの重い遺伝病に加えて、染色体異常が原因の習慣性流産をも、この技術を適用する対象として認める方針を打ち出したのですが、今後、さまざまな論議を呼ぶことが予想されます。
それは、元来、この技術の適用に関しては、賛否があったからです。
一つは、倫理的な問題です。
子宮に戻す受精卵を検査することから、人間が生命の選別にかかわってよいものかという批判です。
また、この技術の適用が、習慣性流産にとどまらずに、男女の産み分けや特別な能力に秀でた遺伝子を子供を産むことに使われることへの懸念もあるからです。
もう1つは、技術そのものの問題です。
検査の精度が100%ではないことや胚から細胞を取り出すことによる劣化への懸念、さらには、長期にわたる子供への影響が未知数であることです。
要するに安全性が十分に確立されていないのではということです。
全ての体外受精の10%で着床前診断が実施されているアメリカでも、安全性を懸念する専門家は少なくありません。
海外においても、原則フリーなアメリカ、条件つきで習慣性流産にも認めているイギリスとオーストラリア以外は、禁じているか、重い遺伝病のみを対象とする国がほとんどです。
いずれにしても、社会的な要請から、この技術を適切に利用するべきでしょうが、今回の日本産科婦人科学会の決定は、学会としてのルールに過ぎず、国が法律に基づいた、ルールを決めるべきではないでしょうか?