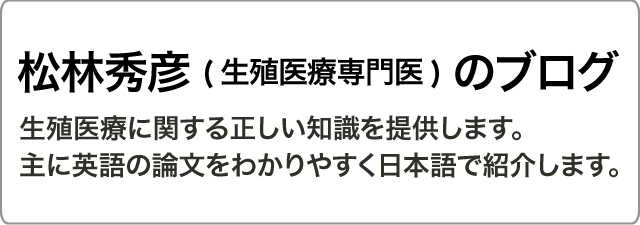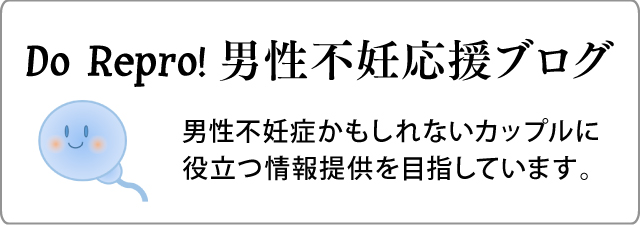試験は、35歳から41歳の体外受精を受けている女性408人を、着床前診断を受けるグループ(206人)と通常の体外受精を受けるグループ(202人)に分けて、836周期(着床前診断は434周期で、通常の体外受精は402周期)の治療成績を比較しました。
その結果、着床前診断を受けたグループの妊娠率は25%で、通常の体外受精を受けたグループの妊娠率37%を下回るものでした。
また、出産に至った割合も、着床前診断を受けたグループは24%で、通常の体外受精を受けたグループの35%を下回る結果となりました。
研究チームの研究者は、なぜこのような結果になったのか明確な原因は不明で、さらなる研究が必要としながらも、着床前診断を実施する際に細胞にダメージを与えること、また、診断の精度の問題(本当に妊娠に至る細胞を選別できているのか)等を指摘しています。
コメント
着床前診断とは、体外受精において、受精卵の染色体を調べて、異常がないと診断された受精卵を選別して子宮に移植する技術のことです。
現在、日本では、日本産科婦人科学会の自主規制によって、重い遺伝病の子への遺伝や習慣性流産の予防目的でのみ実施が許されています。
アメリカやスウェーデンは規制なしで、体外受精の妊娠率を高めるため、流産の防止のため、男女の産み分けのために普通に実施されています。
この現状に対して、現在、開催中のヨーロッパ生殖医学会でこの研究結果が発表された際には、1回の着床前診断にかかる費用が約70万円かかることから、妊娠率の改善につながらない着床前診断を、子を切望する高齢女性の足元をみて実施していることを非難しています。
着床前診断の効果について、今後も研究の推移を見守っていきたいと思います。