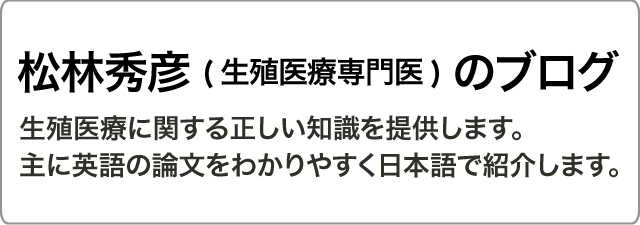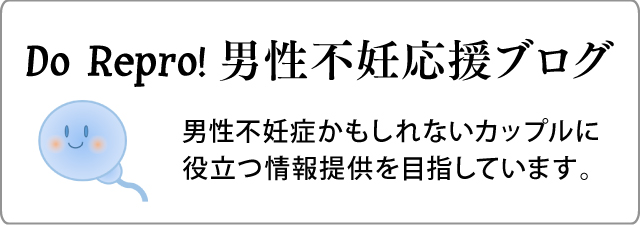また、同時に、凍結融解胚を自然周期で移植しても、ホルモン補充周期で移植しても、その後の治療成績や新生児への影響の大きな違いは確認されませんでした。
1993年から2007年までにコーネル大学病院で、体外受精(720周期)と顕微授精(1231周期)による凍結融解胚移植で妊娠した症例を調べたところ、凍結融解後の胚の生存率は体外受精で74%、顕微授精で77.2%、臨床妊娠率は体外受精で42.8%、顕微授精で39.4%、臨床妊娠後の出産率は、それぞれ、84.1%、89.7%、多胎妊娠率は、それぞれ、27.8%、21.1%、そして、Apgar score(新生児の状態をあらわすスコア)妊娠期間や出生時体重、先天異常の発症率に、大きな差は見られませんでした。
また、自然周期で移植したグループとホルモン補充周期で移植したグループに分けたところ、臨床妊娠率は、自然周期移植で39.4%、ホルモン補充周期移植で2.1%、
臨床妊娠後の出産率は、それぞれ、87.5%、86.7%、そして、妊娠期間や出生時体重、先天異常の発症率においても、大きな差は見られませんでした。
コメント
現在の高度生殖補助医療では、症例数は、顕微授精が体外受精を上回り、胚を凍結保存すること、また、ホルモン補充周期に移植することも当たり前な方法になりました。
つまり、より介入度の大きな治療が一般化しているということが言えます。
それぞれの治療は、当然、必要に応じて施されているものの、介入度の大きな治療の子どもへの影響については常に懸念されるところです。
今回の報告では、凍結融解胚移植において、体外受精でも顕微授精でも、受精時の介入度の違いによる治療成績や新生児への影響の違いは、見られなかったとしています。
そして、自然周期でもホルモン補充周期でも移植周期の違いによる影響も同様です。
まずは、安心できる結果と言えると思います。