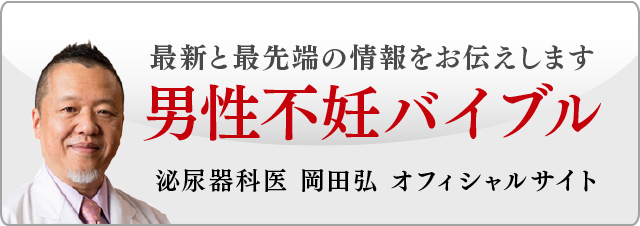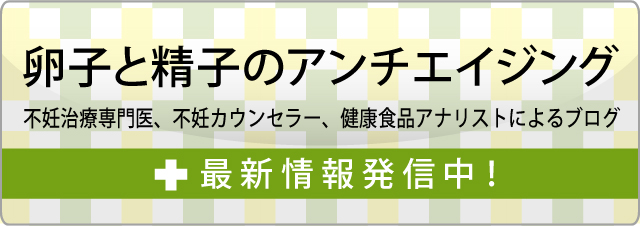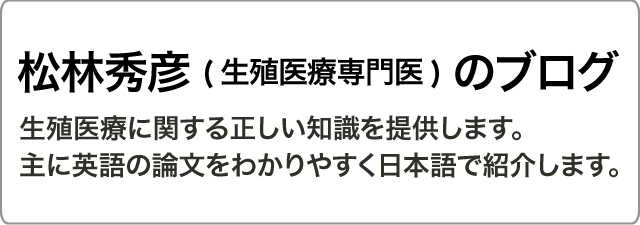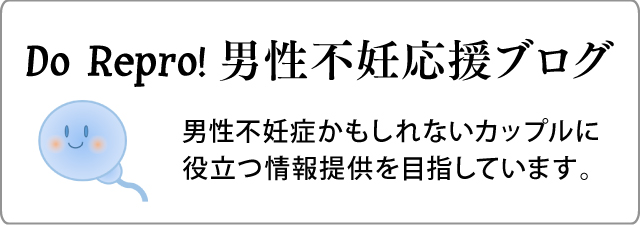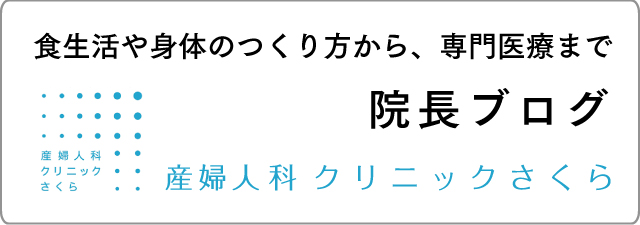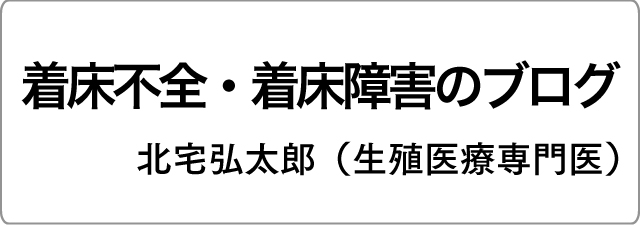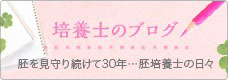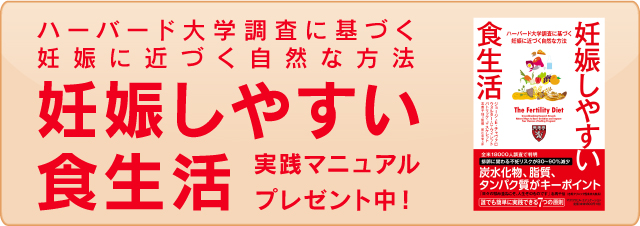ビタミンDは妊娠や出産において重要な栄養素であることが分かってきています。
今回アメリカで行われた研究では、妊娠初期や中期における母親のビタミンDの充足度が、胎児の成長や早産のリスクに関連するかどうかを調べました。
研究ではアメリカの初産婦を対象とした研究から得られたデータをもとに、分析を行いました。研究の対象となった351名の参加者は、妊娠6-13週と16-21週に血中のビタミンD濃度(25(OH)D)を測定しました。胎児の成長は、妊娠16-21週と22-29週に超音波検査で測定し、出生時には身体測定を行いました。
採血の結果、妊娠初期の参加者の20%がビタミンDの欠乏(25(OH)Dが20ng/mL未満)でした。胎児の血中のビタミンD濃度が高くなるほど、胎児の身長が増加することがわかりました。体重や頭囲との関連はみられませんでした。
また妊娠初期のビタミンD濃度が16ng/mL未満の参加者は、32ng/mLの参加者に比べ、早産のリスクが4.35倍であることがわかりました。
妊娠中期のビタミンD濃度については、胎児の成長や早産リスクとの関連はみられませんでした。
結論として、妊娠初期におけるビタミンDの充足度は胎児の成長と関連があり、またビタミンDの不足は早産のリスクの上昇と関連していることが分かりました。
コメント
ビタミンDは健康な妊娠や出産のために重要な脂溶性ビタミンであることがわかってきていますが、この研究では特に妊娠初期に充足させておくことが、胎児の健康な成長や早産リスクの低減に関わることが明らかになりました。
妊娠を望む方にとって、妊娠前から意識してビタミンDの不足に注意する必要があるかもしれません。
近年日本人の不妊治療中の女性を対象に行われた研究では、参加者の93.5%でビタミンDが不足していたという報告がなされています。
日本人は特に紫外線を避ける傾向にありますが、必要な量の多くは紫外線を浴びることで体内でつくられます。特に日照時間の短くなる冬季はさらに不足に注意が必要です。
ビタミンDの充足のためには、意識して日に当たり、また必要に応じてサプリメントでの補充も検討するとよいかもしれません。